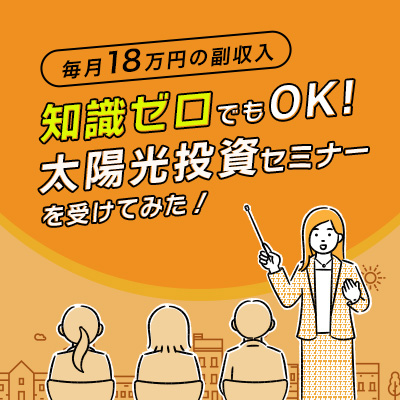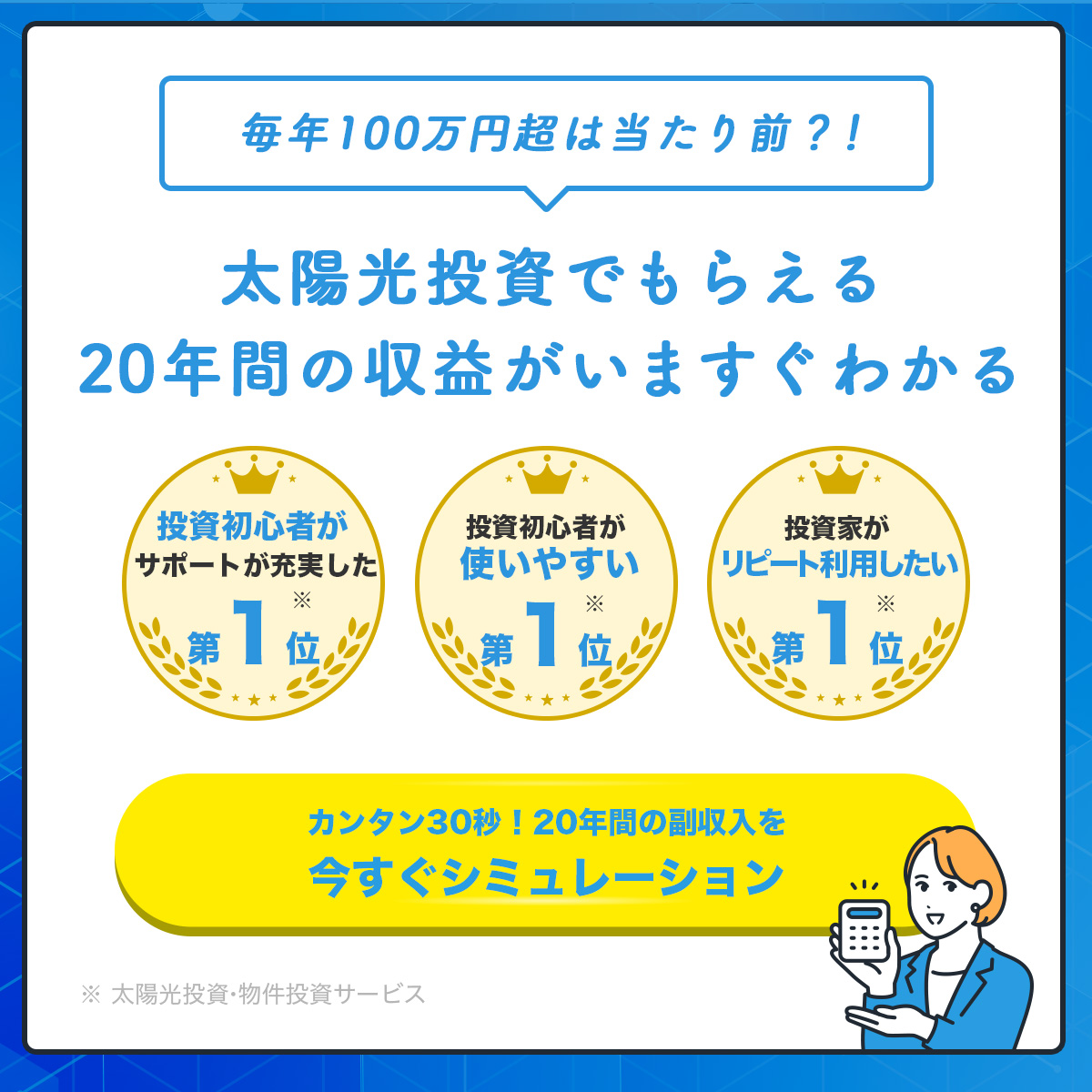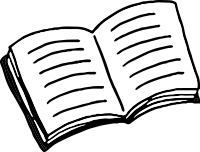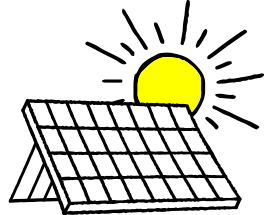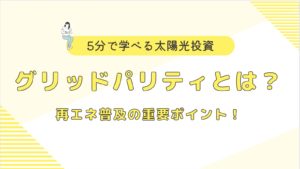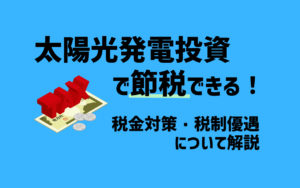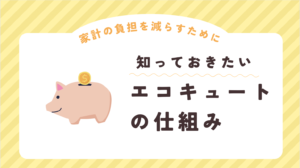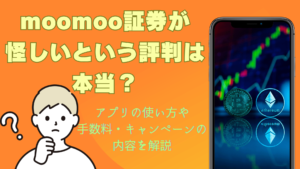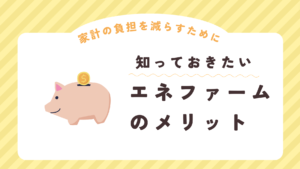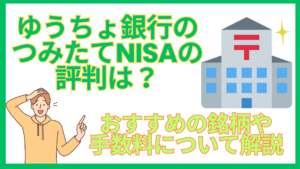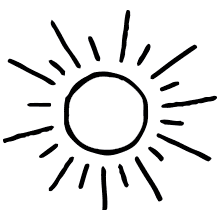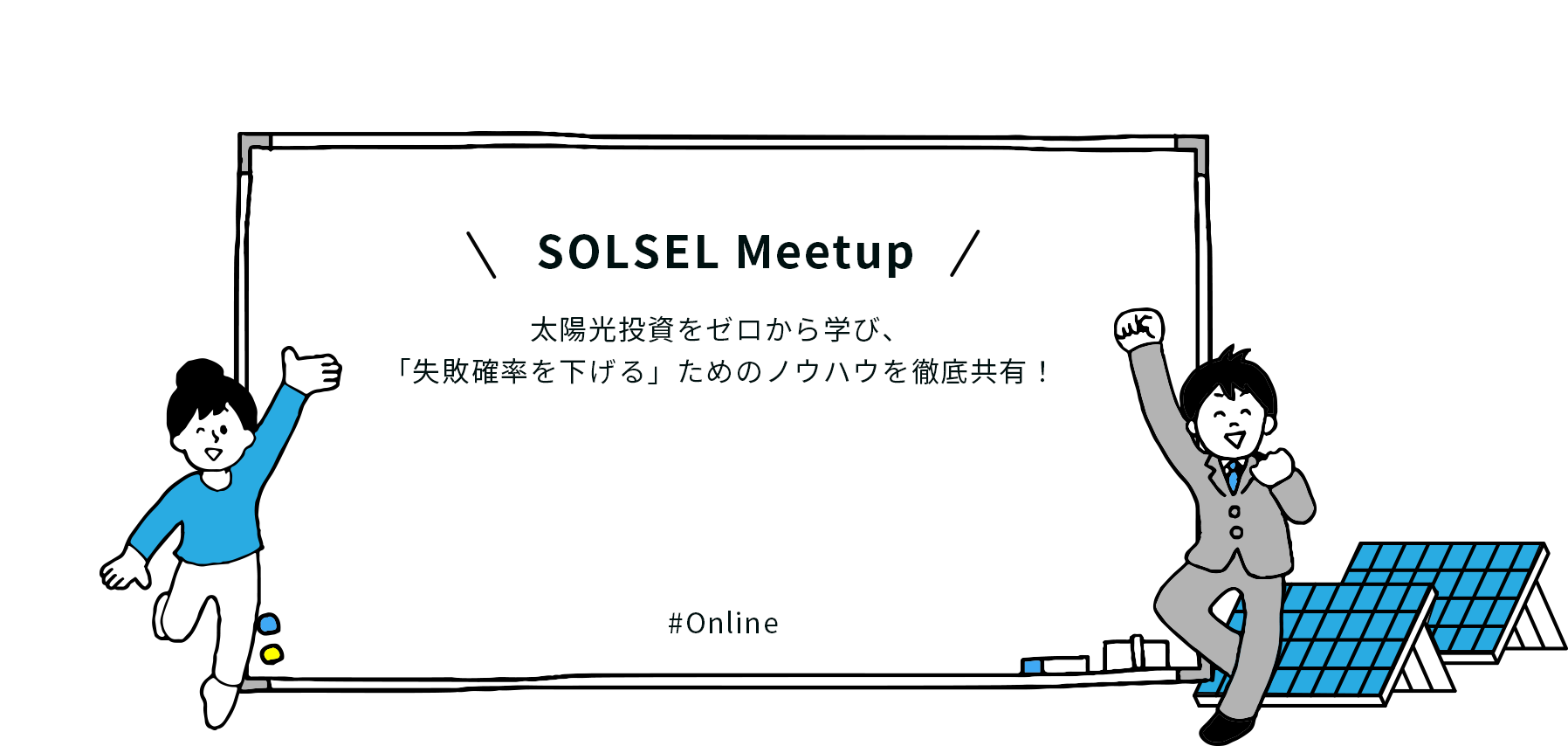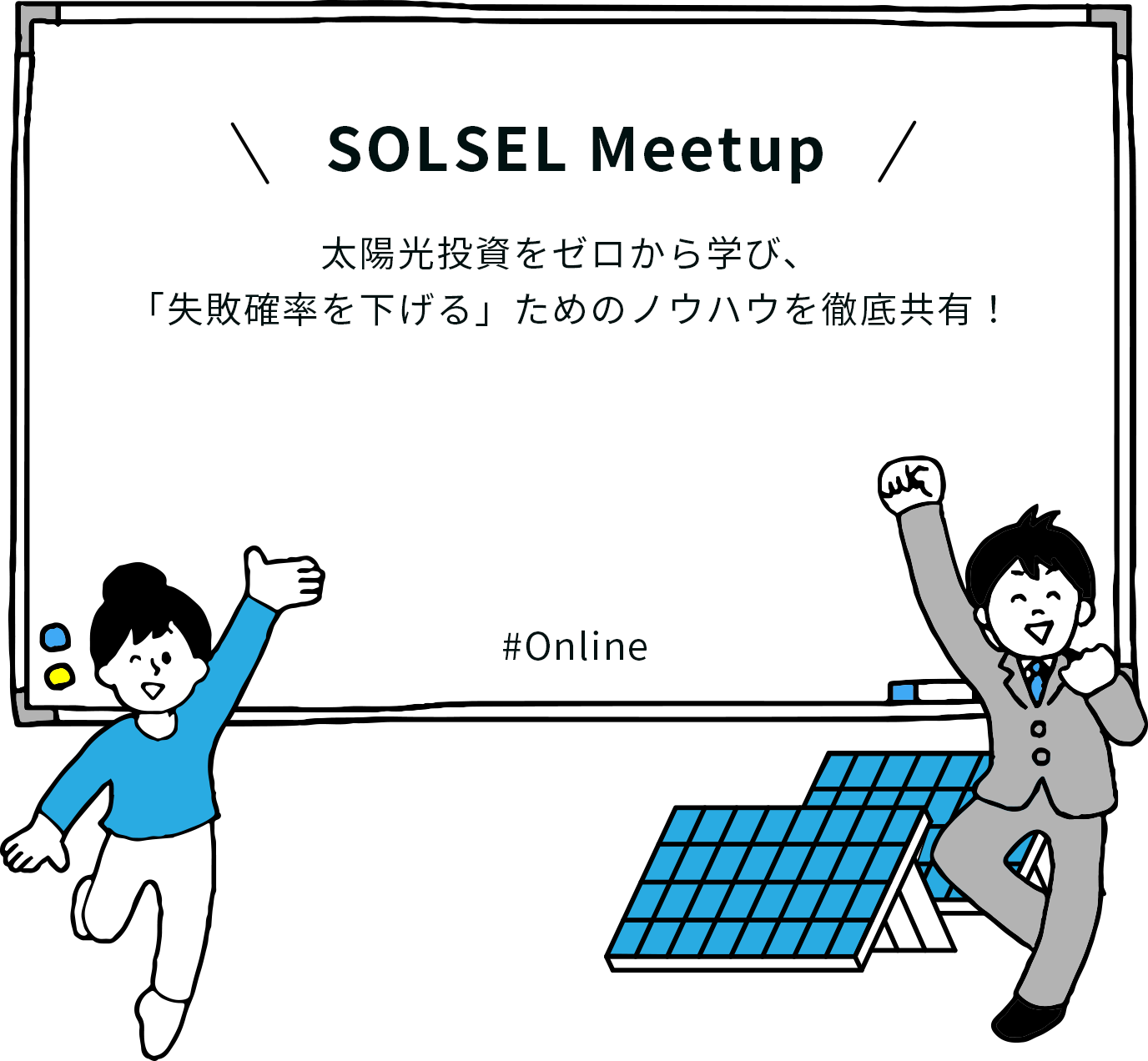NISAはデメリットしかない?メリットとつみたてNISAとの違い・2023年以降どう変わるかわかりやすく解説
個人の資産形成を後押しするため、2014年から導入された少額投資非課税制度のNISA。
本来であれば約20%課税されてしまう投資収益について、限度額までは全て非課税になるという嬉しい制度です。
それなのに、巷ではNISAにはデメリットしかない!という噂があるのを知っていますか?
結論から言うと、NISAにはデメリットもあればメリットもあります。
NISAについてしっかり学んで、メリットとデメリットの両方を理解しておきましょう。
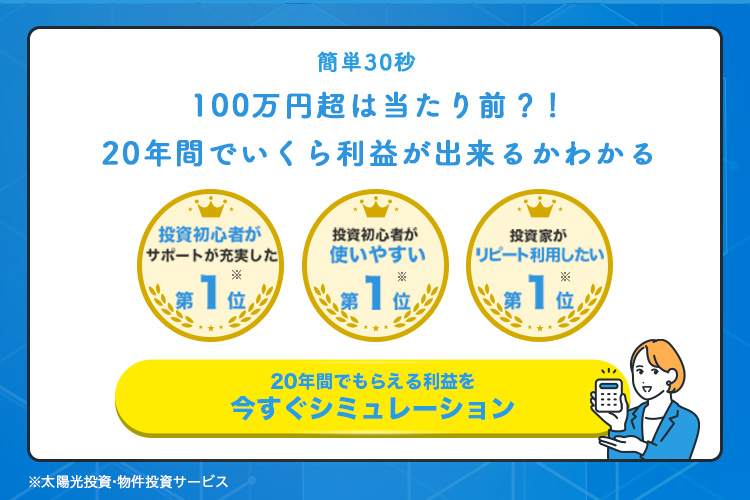
▶︎▶︎完全無料!太陽光投資でいくら儲かる?!◀︎◀︎
NISAとは?

出典:伊予銀行
NISAとは、「Nippon Indivisual Saving Account」の略で、個人向けの非課税口座のことを指します。
金融商品から得た収益や配当金には、通常であれば、20.315%の税金(住民税5%、所得税15%、復興特別所得税0.315%)がかかります。
NISA制度の限度枠内で投資をする分については、その投資から出る収益や配当金については課税されないことになっています。
NISA制度は、非課税の優遇措置を与えて、個人の金融への投資意欲を促進する目的で2014年より導入されました。
まず、従来のNISA制度に一般NISAとつみたてNISAがあることを理解し、その上で、2024年からの新NISAの変更点を整理していきましょう。
なお、現在のNISA制度には一般NISAとつみたてNISAの他に、20歳未満を対象としたジュニアNISAがあります。ただし、ジュニアNISAの新規購入は2023年までとなっていますので、今回の記事では詳しく取り上げません。
つみたてNISAとNISA(一般NISA)の違い
一般NISAとつみたてNISAの違いを表にまとめると以下の通りです。
| 一般NISA | つみたてNISA | |
| 毎年の非課税枠 | 120万円 | 40万円 |
| 総非課税枠 | 600万円(=120万円×5年) | 800万円(=40万円×20年) |
| 非課税運用期間 | 5年間 | 20年間 |
| 口座開設期間 | 2023年まで | 2023年まで |
| 投資対象品 | 上場株式・ETF・公募株式投信・REIT等 | 一定の投資信託
(金融庁への届け出が必要) |
| 買付方法 | 通常の買付・積立 | 積立のみ |
((注)金融庁HP NISA特別Webサイトより)
NISA制度には、一般NISAとつみたてNISAがあります。
「NISA」とは、つみたてNISAやジュニアNISAまで含んだNISAの仕組み全体を指す場合と、一般NISAを指す場合があります。
この記事では、違いを分かりやすくする為に、つみたてNISAやジュニアNISAまで含んだものを「NISA制度」、一般NISAのことを単に「NISA」または「つみたてNISA」と併用する時には「一般NISA」と呼ぶことにします。
一般NISAとつみたてNISAにはどのような違いがあるのでしょうか。
まず、課税されず運用できる年間の非課税枠については、一般NISAは120万円であるのに対し、つみたてNISAは40万円となっています。
課税されずに運用できる期間は、一般NISAが5年間、つみたてNISAが20年間です。
投資できる対象も、一般NISAは上場株式やETF、REITなど幅広いですが、つみたてNISAは長期分散投資に適した積立型の投資信託のみ、といった違いがあります。
つみたてNISAの場合、公募株式投資信託は販売手数料がゼロで信託報酬が一定額以下のものに限られています。
一般NISAはまとまった資金で積極的な運用をしたい人向け、つみたてNISAは投資初心者や少額で長期に安定運用をしたい人向け、と言えます。
NISAは2024年から新NISAに移行する?
2024年からNISAは新しくなります。
内容が大幅に変わり、名称も変更となるため、分かりにくい!と混乱してしまう人もいるかもしれません。
新NISAの主な改正点を表にまとめると以下の通りとなります。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
| 毎年の非課税枠 | 240万円 | 120万円 |
| 総非課税枠 | 1,800万円 (ただし、成長投資枠で1,200万円まで) |
|
| 非課税期間 | 無期限 | |
| 口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
| 投資対象品 | 上場株式・ETF・公募株式投信・REIT等 | 一定の投資信託 (金融庁への届け出が必要) |
| 買付方法 | 通常の買付・積立 | 積立のみ |
新NISA改正の大きなポイントを確認しておきましょう。
- 年間で投資できる金額が大幅にアップ(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)
- つみたて投資枠と成長投資枠の同時併用が可能(年間投資枠は合わせて360万円)
- 非課税で運用できる期間ならびに口座開設期間が無期限化
- 非課税保有限度枠は総枠で1,800万円まで
非課税で投資できる年間の金額が2~3倍にアップした代わりに、1人あたりの総投資額は無期限で1,800万円まで、という新しい制限ができました。
老後に必要な資金は1人あたり約2,000万円、と言われていますから、新NISAを利用することで、非課税のメリットを生かしながら、老後資金を準備することができます。
気になるのは、現在NISA口座を保有している人がどうなるかです。
現在保有している一般NISAやつみたてNISAがある場合、購入してから非課税で運用できる期間(一般NISAで5年、つみたてNISAで20年)が終了するまでは、課税されることなく保有できます。
現行のNISAの非課税枠と新しく始めるNISAの非課税枠は別々にカウントされます。
例えば、現在NISAで500万円枠を使っているからと言って、新NISAの枠がその分減額されるということはありません。
ただし、今保有している金融商品を新NISAの口座にロールオーバーすることはできませんので注意してください。
ロールオーバーとは?
ロールオーバーとは、一般NISAの非課税期間5年が終了した時点で、口座内にある金融商品を、新たなNISA口座に移管することです。
ロールオーバーを利用することで、実質的に課税されない期間を10年まで延長することができます。
ただし、ロールオーバーする金額が120万円を超えていた場合は、その年の非課税枠をすべて消費してしまうことになります。ですから、非課税枠内で新たに金融商品を購入することはできません。翌年以降は、再度年間120万円の非課税枠が適用されます。
また、現行のNISAで保有している金融商品を新しいNISAにロールオーバーすることもできません。
現行のNISA口座の商品は、非課税期間が終了するまでに、NISA以外の口座に移すか、売却するかのいずれかを選択する必要があります。
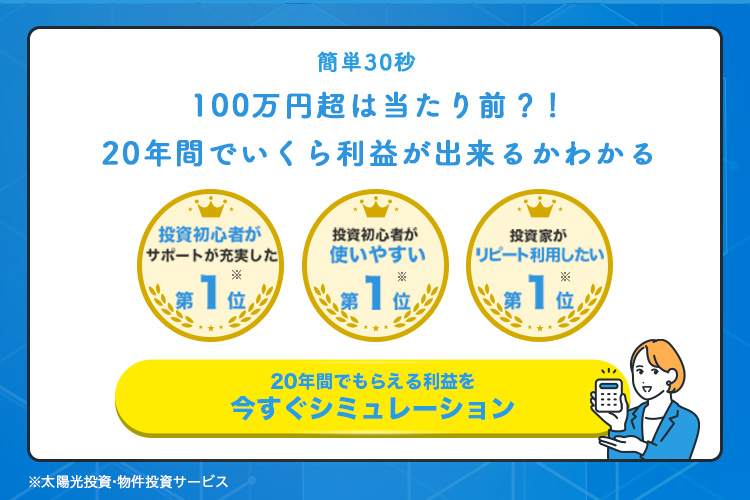
▶︎▶︎完全無料!太陽光投資でいくら儲かる?!◀︎◀︎
NISAはデメリットしかないって本当?

個人の投資を促進するために導入されたNISAなのに、「デメリットしかない」という声が聞かれるのはなぜでしょうか?
調べてみると、確かにNISAには幾つかのデメリットがあります。
NISAの主なデメリットについてまとめると、以下のようになります。
- 1人につき1口座しか開設できない
- 元本割れの可能性がある
- 損益通算と繰越控除ができない
- 損失が出た場合の税金対策ができない
- 非課税枠を使い切っているとスイッチングができない
- 2023年までの購入分は新NISAにロールオーバーできない
- 国内居住者かつ20歳以上でないと開設できない
順番に詳しく解説していきましょう。
1人につき1口座しか開設できない
現行のNISA制度では、全金融機関で1人につき1口座しか開設ができません。
銀行や証券会社を変えても、NISA口座は1つだけしか保有できないのです。
ジュニアNISAだけでなく、一般NISAとつみたてNISAに同時加入することも不可です。
当然、非課税枠も合算できませんし、まとまった資金の投資と積立の投資を両方同時に行ないたい、というニーズにも対応できなくなっています。
しかし、先に説明したように、2024年から始まる新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能です。
総額で1,800万円までであれば、成長投資枠とつみたて投資枠の両方で運用でき、非課税枠内であれば、積極的な資金運用と長期分散の積立投資を並行して行うことができます。
元本割れの可能性がある
預金とは違いますので、価格変動リスクがあり、元本割れする可能性があります。
金融庁が推奨する制度なので安心だ、と誤解している人がいますが、収益が非課税なだけで、投資の成果や元本を保証するものではありません。
投資商品を選択するのは口座開設者本人であり、対象商品は民間の株式や投資信託ですから、元本は保証されておらず、投資のリスクはあることは理解しておきましょう。
損益通算と繰越控除ができない
税法上、株式や投資信託などから得た収益については、他の口座での投資損益と合算できる「損益通算」という仕組みがあります。
例えば、証券口座Aで10万円の損失、証券口座Bで30万円の利益が出たとします。
損益通算をすれば、AとBの口座を合わせて税法上の利益は20万円となり、この20万円に対して20.315%課税されることになるのです。
これが個別に課税されたら、証券口座Bの30万円の利益に約20%課税されることになってしまいますが、損益通算をすることで、10万円分の利益を圧縮して、税金を減らすことができるというわけです。
しかし、この損益通算を、NISAとNISA以外の口座ではできないことになっています。
また、NISA以外の口座では、最終的に損失が残った場合、3年間は翌年以降の利益から損失分を控除できる、繰越控除の制度があります。
繰越控除を使えば、翌年以降利益が出た時に残った分の損失を相殺し、利益を圧縮して税金を少なくすることができます。
もし投資で儲かって税金が多くなってしまいそうな時でも、繰越控除が使えれば税金対策にもなります。
しかし、NISAでは、損益通算だけでなく、この損失の繰越控除もできないことになっています。
NISA口座は非課税という優遇措置を受けているため、他の口座との損益通算や繰越控除ができない仕組みになっているのです。
損失が出た場合の税金対策ができない
NISAでは、他の口座との損益通算や繰越控除ができないため、損失が出た場合でも税金対策ができません。
通常の口座で投資を行なった場合は、損失が出た場合、損益通算して他の投資利益と相殺したり、翌年以降に利益が出た場合に繰越控除をして、利益を圧縮することができます。
利益が出ている時に非課税なのは良いのですが、損失が出た場合には一般の口座での投資と比べてデメリットが多いのが、NISAの特徴です。
投資で損が出た場合は、NISAで投資しない方が良かった、ということになりかねません。
非課税枠を使い切っているとスイッチングができない
スイッチングとは、今現在保有している株や投資信託などの金融商品を一旦売却して、他の金融商品に「買い替え」をすることです。
NISA口座では、スイッチングをする場合でも、非課税枠の計算の仕方が、新たに金融商品を購入するのと同じ扱いになります。
つまり、10万円分の金融商品をスイッチングしたとすると、その年の分の非課税枠を新たに10万円分使ってしまうことになるのです。
ですから、もし既にその年の分の非課税枠120万円を使い切ってしまっている場合、非課税枠内でスイッチングをしたければ、翌年まで待たなければいけないことになります。
2023年までの購入分は2024年の新NISAにロールオーバーできない
先に述べたように、2024年からNISAは大幅な制度改正がされます。
非課税枠が拡大し、非課税期間も無期限になる、というメリットがありますが、従来のNISAで購入した分を新NISAにロールオーバーすることはできません。
ただし、2023年までにNISA口座で購入した商品は、非課税期間が終了するまでは、新NISAとは別枠で保有することができます。
例えば、2023年にNISAで120万円の投資信託を購入した場合、5年後の2028年までは非課税の措置が受けられることになります。投資した人は、2028年に非課税期間が終了した時点までに、売却するか、一般の口座に移管するかを選択することになります。
国内居住者かつ18歳以上でないと開設できない
NISAの口座が開設できるのは国内居住者かつ18歳以上の人です。
海外居住中の人は、口座開設ができません。
NISA口座を開設した後で海外赴任などをする場合は、届出をすることにより5年間だけ非課税措置を受けられますが、5年を超えても帰国しなかった場合は、NISA口座は解約されてしまいます。
18歳未満を対象としたNISAにはジュニアNISAがありますが、新規開設は2023年までとなっています。
一般NISAやつみたてNISA、新NISAの口座については、18歳以上の人しか開設できません。
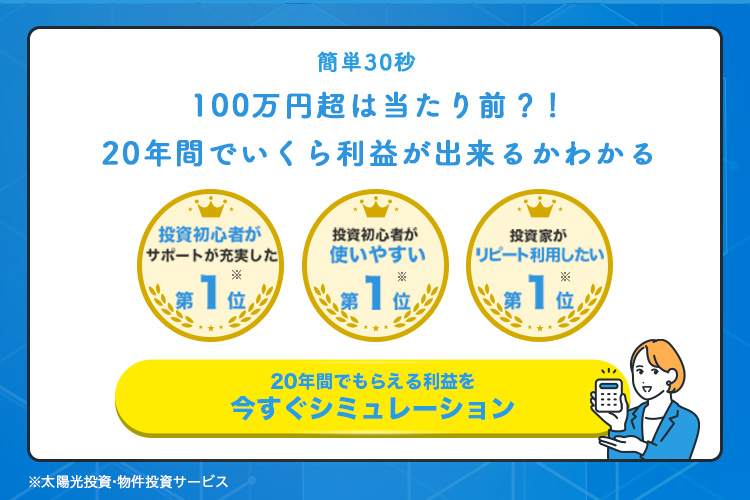
▶︎▶︎完全無料!太陽光投資でいくら儲かる?!◀︎◀︎
NISAにもメリットがある!安定投資を始めたい人におすすめ

NISAはデメリットしかない、と言う人がいますが、メリットはないのでしょうか?
もちろん、NISAには大きなメリットがあります。
NISAの主なメリットは以下のようなものです。
- 利益は非課税
- 少額からでも投資できる
- リスク分散できる
- 非課税期間が終了したらロールオーバーできる
- 換金しやすい
- 確定申告不要で便利
順番に1つずつ見ていきましょう。
利益は非課税
NISAにおける最大のメリットは、何といっても、非課税限度枠120万円までの投資についての利益が全て非課税になることです。
非課税期間は5年間ですから、120万円×5年間=合計600万円までの投資による利益が非課税になります。
つまり、投資総額600万円までは、利益がいくら出ても税金はかからないということです。
例えば、600万円の金融商品が20%値上がりして売却利益は120万円だった場合、約20%課税されると税金は24万円ですが、NISAであれば、この24万円分が非課税になります。
売却益120万円で税金が約24万円というのはかなり大きな額ですので、せっかく投資で利益が出ても、税金がかかってしまっては元も子もありません。
金融商品の利益は、通常、預金の利息のようなものでも約20%(2037年までは復興特別所得税0.315%が加算)の課税対象です。
預金の金利などは源泉徴収なので気づかないかもしれませんが、金利0.5%の預金であっても、利息の中から約20%の税金がしっかり徴収されています。
100万円の預金で利息が5千円だとすると・・・そこからさらに1千円以上(5,000円×20.315%=1,015円)税金が引かれてしまうのです。
また、NISAの非課税限度枠は投資する金額についての枠であり、利益額の枠ではありません。
つまり、120万円までの投資であれば、利益が120万円を超えて、さらに200万円、300万円の利益になろうが、全て非課税になるのです。
理論上は、利益額がいくらになっても課税されないということなので、利益額が大きくなればなるほど、NISAの非課税メリットはさらに大きくなると言えます。
少額からでも投資できる
NISAの最小投資額は、商品によって異なりますが、証券会社によっては100円単位から購入できるものもあります。
元々、個人の少額からの投資を促進する目的でつくられた制度ですから、数千円単位の少額からでも投資が始められるのは、NISAの大きなメリットと言えます。
リスク分散できる
投資対象商品が上場株式から投資信託、REIT、ETFまで幅広く、リスク分散がしやすいことも、メリットの1つです。
一般NISAであれば、株式やETFは国内でも海外でも選ぶことができますし、REITや債券や新興国株を組み入れた投資信託なども選択できます。
投資対象の国や地域、商品などを選んでリスク分散できる上、毎月分配型やインデックス型など、様々な投資信託を選ぶことができるのがNISAの魅力です。
非課税期間が終了したらロールオーバーができる
従来のNISAは非課税期間が5年までと定められていましたが、この5年を過ぎても、ロールオーバーすれば、また最長で5年間非課税の適用が受けられます。
ただし、2023年末までに非課税期間が終了する人が対象となります。つまりこれから(2023年から)NISAを始める人はロールオーバーできません。
NISAは非課税期間内に売却益が出ても課税されませんが、損が出た場合には、他の口座と損益通算や翌年以降に損失を繰越すことができません。
ロールオーバーができれば、非課税期間終了時に無理やり売却をしなくても、自分にとって都合の良いタイミングで売却できる、というメリットがあります。
換金しやすい
NISAの商品は換金しやすい、というのも大きなメリットです。
比較的手数料などが安い投資商品がラインナップされている上、株や投資信託などいつでも売却して換金することができます。
個人の資産形成で税制優遇を受けられるものとして、iDeCo(個人型確定拠出年金)がありますが、iDeCoの場合は老後の資産形成を目的としている為、原則60歳までは資金の引き出しができません。
『長期運用を前提とした金融商品は、引き出しの制限やペナルティがあるものが多いね』
その点、NISAはいつでも自由に引き出しができ、資金使途の指定も無いので、換金性と自由度が高いと言えます。
確定申告不要で便利
NISAは原則、確定申告不要で非課税措置を受けられます。
通常はサラリーマンでも、給与所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告が必要です。
その点、NISAの場合はどんなに利益が出ても非課税ですので、確定申告をする煩わしさがありません。
ただし、例外的に以下の2つのケースでは、確定申告が必要となりますので注意しましょう。
- 非課税期間が終了してロールオーバーしない場合
- 配当金の受取で「株式数比例配分方式」以外の方法を選択した場合
NISA口座が開設できるおすすめのネット証券
NISA口座が開設できるネット証券のうち、おすすめのネット証券をご紹介します。
SBI証券

| 手数料 | 無料(外国株は有料) | |
| 取扱商品 | 国内株 | ◯ |
| 海外株 | ◯ (米国・中国・韓国・ロシア・ベトナム・インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア) |
|
| 投資信託 | 約2,580銘柄 | |
| NISAでのIPO対応 | ◯ | |
- 商品のラインナップが豊富
- 外国株式はネット証券最多
- 夜間取引が可能
SBI証券の一般NISAでは、商品ラインナップの充実度は主要ネット証券の中ではトップクラスです。
国内株式は国内4市場に上場する銘柄、単元未満株やIPOにも対応しています。米国株の取り扱いについても、主要ネット証券最多となっています。
SB I証券では、PTS取引ができるため、夜間であっても取引が可能です。PTS取引とは、取引所を経由せずに株式を売買できる取引のことです。
東京証券取引所で売買できる時間は、平日9時〜11時30分と12時30分〜15時の間のになります。PTS取引ができれば、時間を気にすることなく取引できるため、日中は仕事で取引できないという人におすすめです。
マネックス証券

| 株式売買手数料(税込) | 無料 | |
| 取扱商品 | 国内株 | ◯ |
| 海外株 | ◯(米国・中国) | |
| 投資信託 | 約1,260銘柄 | |
| NISAでのIPO対応 | ◯ | |
- 商品のラインナップが豊富
- 米国株や中国株(香港株)に強い
- 米国株・香港株、海外ETFの買付手数料が残額キャッシュバックされる
マネックス証券の一般NISAは、国内株式・外国株式・投資信託の取扱いがあります。中でも、米国株と中国株(香港株)に強く、香港株については香港市場に上場するほぼ全ての銘柄の取引可能です。これらへの投資を主に考えている人にはおすすめの証券会社です。
また、マネックス証券の一般NISAでは、東証と名証の上場銘柄の単元未満株取引にも対応しています。NISAの非課税投資枠をうまく活用して投資をしたい人は、マネックス証券を検討してみましょう。
DMM株

| 株式売買手数料(税込) | 無料 | |
| 取扱商品 | 国内株 | ◯ |
| 海外株 | ◯ | |
| 投資信託 | × | |
| NISAでのIPO対応 | − | |
- スマホでも操作が可能
- NISAの取扱いは一般NISAとジュニアNISAのみ
DMM株は、日本の各証券取引所の上場銘柄と、米国株約2,000銘柄を扱っています。また、NISA口座での取引の場合、全ての取引手数料が無料になります。
口座開設手続きは、Web上で完結できます。アプリやWebでアップロードする場合はマイナンバーを提出できるため、手続きがスピーディーに。
DMM株では、一般NISAとジュニアNISAは取扱っていますが、つみたてNISAは取り扱いがないため、一般NISAから切り替える可能性がある場合には注意が必要です。
auカブコム証券

| 株式売買手数料(税込) | 無料 | |
| 取扱商品 | 国内株 | ◯ |
| 海外株 | × | |
| 投資信託 | 約1,590銘柄 | |
| NISAでのIPO対応 | ◯ | |
- 100銘柄のETFも手数料無料
- 投資信託は100円から購入可能
- Pontaポイントが貯まる・使える
auカブコム証券は、名の通りauユーザーにお得なサービスが満載です。
例えば、ポイント還元率がアップする「投資信託ポイントプログラム」や月間保有残高に応じてもらえる「資産形成プログラム」、au PAYカードで決済すると毎月Pontaポイントがもらえるなど、特典が豊富にあります。
auカブコム証券は日本の各証券取引所の上場銘柄と投資信託、単元未満株の取り扱いがあり、少額から投資ができます。
口座開設にはWeb完結できますが、郵送での手続きも可能です。
松井証券

| 株式売買手数料(税込) | 無料 | |
| 取扱商品 | 国内株 | ◯ |
| 海外株 | △(米国株) | |
| 投資信託 | 約1,640銘柄 | |
| NISAでのIPO対応 | ◯ | |
- ロボアドバイザーがいて初心者に優しい
- 株式の取引手数料が永久的に無料
- コールセンターのサポートで安心
松井証券は、1日の現物取引や信用取引の合計が50万円以下であれば、手数料無料で取引が可能です。さらに、25歳以下であれば、金額関係なく現物取引・信用取引ともに手数料がかかりません。
また、コールセンターによるサポートが定評で、どんな質問にもわかりやすく丁寧に説明してもらえます。始めたばかりでよくわからない人や不安がある人は、一度コールセンターに電話をしてみると良いでしょう。
松井証券では、ロボアドバイザー「投信工房」が最適な投資プランを提案してくれます。そのため、初心者でも投資を始めやすくなっています。
楽天証券
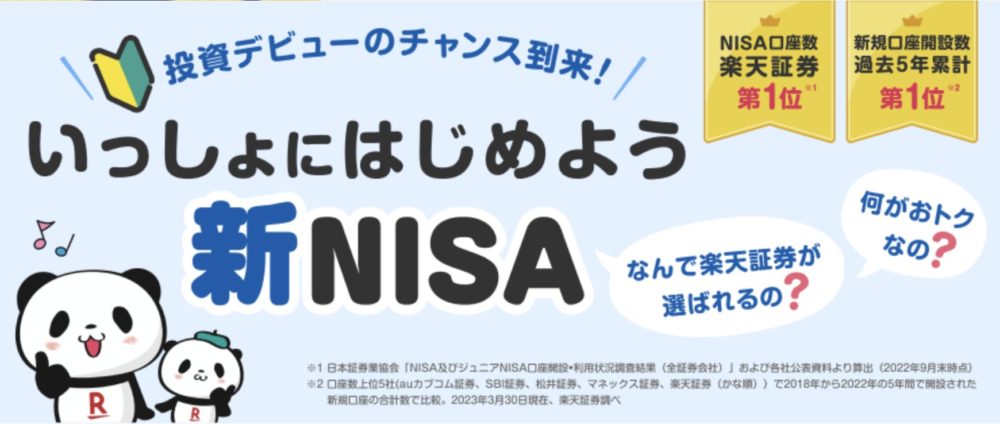
| 株式売買手数料(税込) | 無料 | |
| 取扱商品 | 国内株 | ◯ |
| 海外株 | ◯(米国・中国・インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア) | |
| 投資信託 | 約2,550銘柄 | |
| NISAでのIPO対応 | × | |
- 初心者でもわかりやすいサービスが揃っている
- 楽天ポイントが貯まりやすい
- 株アプリ「iSPEED」が使いやすい
楽天証券では、国内株式・外国株式ともに、多くの商品がNISA対象となっています。
国内株式での売買手数料は無料、海外ETFの買付手数料に関しても全額キャッシュバックされ、コストを抑えながらも豊富な銘柄の中から選ぶことができます。
楽天証券の株アプリ「i SPEED」の活用で、銘柄の動向なども簡単にチェックできます。ログインして利用することで、お気に入り銘柄などを記録したり、自分好みに設定することもできますが、ログインなしでも利用できるので、口座開設前に使ってみるのもおすすめです。
NISAを始めるときの注意点

NISAには、デメリットとメリットの両方があることが分かりました。
非課税制度を受けながら資産形成ができる便利なNISAですが、始める際にはいくつか注意しなければならない点があります。
NISAを始めるときの注意点についてまとめました。
新規に購入した商品のみが対象
NISAの非課税制度は、NISA口座内で新たに購入した金融商品だけが対象となっています。
NISA口座開設前に保有している株式や投資信託をNISA口座に移すことはできません。
今現在保有している金融商品がある場合は、全体の資産のバランスを見ながら、NISA口座の購入額や商品を決めるようにしましょう。
非課税枠の繰越はできない
NISAの非課税枠は一般NISAが年間120万円、つみたてNISAが年間40万円となっています。
この年間非課税枠は未使用分があっても翌年以降に繰り越すことはできません。
非課税枠を最大限に利用したい場合は、毎年非課税枠いっぱいまで投資するようにしてください。
つみたてNISAの場合は、毎月同じ積立額だと端数が出てしまうので、ボーナス月には積立額を増額する設定をすると良いでしょう。
損失が出た場合に節税方法がない
NISAのデメリットで挙げた通り、NISA口座は他の口座との損益通算や、損失の繰越ができません。
従って、利益が出ている場合は良いですが、損失が出た場合の節税する方法が全く無いことになります。
NISAの投資商品は、できるだけ安定的な損失の出やすい商品を選んだ方が良いでしょう。
▶︎関連記事:「太陽光発電投資でできる節税・税金対策・税制優遇を徹底解説【知らないと損!】」
売却するタイミングに注意
NISAでは、損失が出た時に税金対策ができない為、保有商品を売却するタイミングには注意が必要です。
NISAの非課税期間が終了した場合、一般の口座に移すか、ロールオーバーするか、売却するかのいずれかを選択することになります。
保有している商品が値上がりして売却益が出る場合は非課税のメリットを享受できますが、値下がりしていて損が出た場合は税金対策ができないので、ロールオーバーした方が良いかもしれません。
(ただし、2023年末までに非課税期間が終了する人が対象となります。つまりこれから(2023年以降)NISAを始める人はロールオーバーできません)
ただし、ロールオーバーできるのは1回だけです。
そのため、1度ロールオーバーしている人は、次の期間終了時と保有商品の価格推移を勘案して、売却タイミングを考えた方がいいでしょう。
また、一般の口座に移した場合、保有している金融商品は一般の口座に移した時点の価格に評価が変わります。つまり、50万円で購入した株式が、非課税期間終了時に40万円に値下がりしていて、そのまま一般口座に移管された場合は、評価額が40万円に変わります。
この後、再び価格が50万円に戻って、購入時からすれば収益はゼロ円だとしても、税金上の収益は10万円となって課税されてしまうのです。
NISAの購入商品は、基本的にいつでも売却できますので、価格変動や非課税期間の終了時期などを勘案し、売却タイミングを決めることが必要です。
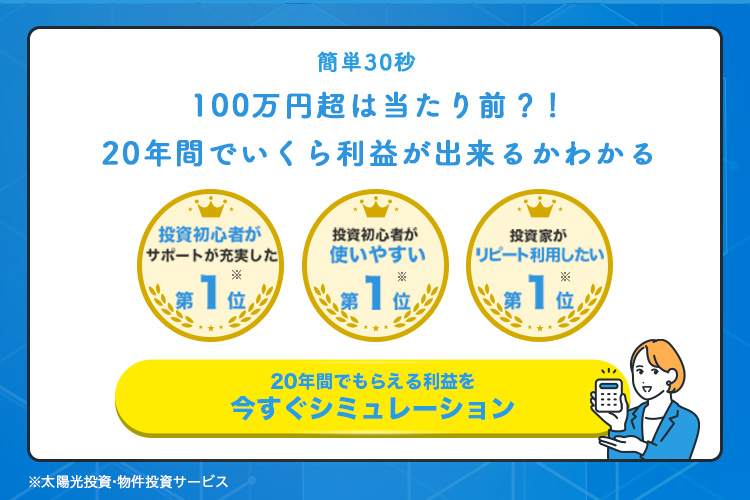
▶︎▶︎完全無料!太陽光投資でいくら儲かる?!◀︎◀︎
NISAに関するよくある質問

運用次第でメリットもデメリットもあるNISA。
始める前に疑問点についてしっかり確認をしておくことが大切です。
NISAに関して、よくある質問をQ&A方式でまとめてみました。
NISA口座を複数の金融機関で開設することはできる?
NISAの口座は、1人1口座しか開設できません。
今あるNISA口座を別の金融機関に移す事は可能?
金融機関を変更することは可能です。
ただし、金融機関の変更は年単位となっていますので、注意してください。
金融機関を変更する場合は、変更する年の9月30日までに、変更の手続きを完了する必要があります。
手続きの詳細については事前に金融機関に確認をしておきましょう。
NISA口座を家族でまとめて契約したり、子供の名義で契約できる?
NISAの契約は個人ごとに行うことになっていますので、共同名義や家族で契約をすることはできません。
子供については、18歳以上の国内居住者であれば個人名義で契約ができます。
17歳以下を対象としたジュニアNISAについては、2024年で廃止が決定しています。
NISAで購入できる商品は金融機関によって違うの?
NISAで投資できる商品は金融機関によって異なります。
一般NISAでは、国内外株式、国内外ETF、国内外の投資信託のほか、J-REIT、海外REIT、ETF(上場投資証券)、新株予約券付社債などを購入できます。
債券や公社債投資信託は対象になりませんので注意してください。
つみたてNISAでは、長期の積立、分散投資に適した投資信託で、金融庁に届け出をしたものが対象となります。
いまある保有商品をNISA口座に移したり、非課税措置を受けることは可能?
現在保有している商品を、NISA口座に移すことはできません。
NISAでは新規に購入した金融商品のみが非課税措置の対象となります。
いま他の口座で保有している金融商品をNISA口座に移管したり、保有している金融商品に対して非課税措置を受けることはできません。
NISA口座開設にマイナンバーは必要か
NISA口座の開設には、マイナンバーが必要です。
2016年以降、新たにNISA口座を開設する場合には、金融機関に対しマイナンバーの告知を行う必要があります。
NISAの口座開設には、「個人番号カード」もしくは「通知カード+写真あり本人確認書類」の提示が必要となります。
つみたてNISAからNISAに切り替えることはできるか
年1回に限り、つみたてNISAからNISAへ、あるいはNISAからつみたてNISAへ切り替えを行うことができます。
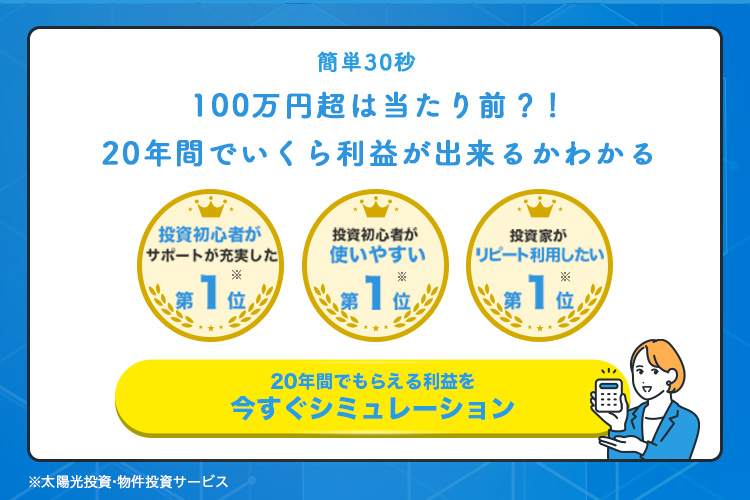
▶︎▶︎完全無料!太陽光投資でいくら儲かる?!◀︎◀︎
まとめ
以上、NISAにはデメリットしかない?という噂の真相について調べてみました。
NISAにはメリットとデメリットの両方があるので、どんな場合にデメリットが生じるかよく理解しておくことが大切です。
特に、NISAの投資で損失が出たり、売却タイミングを間違えてしまうと、デメリットが生じてしまうので、注意しましょう。
2024年からは新たなNISA制度が始まり、投資枠が大幅に拡大されます。
便利なNISA制度のメリットとデメリットについてしっかり把握して、自分が投資するべき商品やタイミングを判断するようにしましょう。
NISAやつみたてNISAは仕組みが複雑であるため、難しいと思っている方は少なくないかと思います。さらに2024年からは新NISAも始まるため、より一層苦手意識を持ってしまう方もいるかもしれません。
ただし、NISA制度はしっかり活用することで、資産形成に大きく役立つ制度です。少額からの投資も可能なので、まずは口座開設から始めてみてください。最近ではオンラインで口座開設できる金融機関がほとんどなので、忙しい方でも気軽に口座開設ができます。
NISA制度を活用して人生100年時代を生きていくための資産形成作りをしていきましょう。

マネーエスコート代表 1級ファイナンシャルプランニング技能士
新卒で大和証券へ入社後、みずほ銀行など5社へ転職し、FPコンサルティング部部長や社長室室長などを経て独立。
金融機関の執筆記事の監修や、不動産会社でのセミナー講師、金融機関向けの動画制作など実績多数。金融初心者からは「難しいテーマでもわかりやすく理解できる」と好評。家計見直しや生活に役立つ情報サイト「マナブロ」も運営中。
公式HP:https://www.money-escort.tokyo/
マナブロ:https://manablo.com/
参考サイト:
金融庁NISA特設ウェブサイト
ダイヤモンドZAI ONLINE
日本証券業界JSDA
クラウド会計ソフトfreee
日本証券業界 一般NISAに関するQ&A
SOLACHIE presents
-
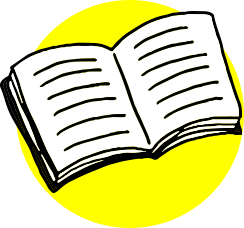
太陽光投資の「失敗確率を下げるノウハウ」を一冊の本に!無料の限定資料をプレゼント
-

投資スタートした場合の、実際の利回りシミュレーションをプレゼント
-

太陽光投資プラットフォーム「SOLSEL」非公開物件をご紹介